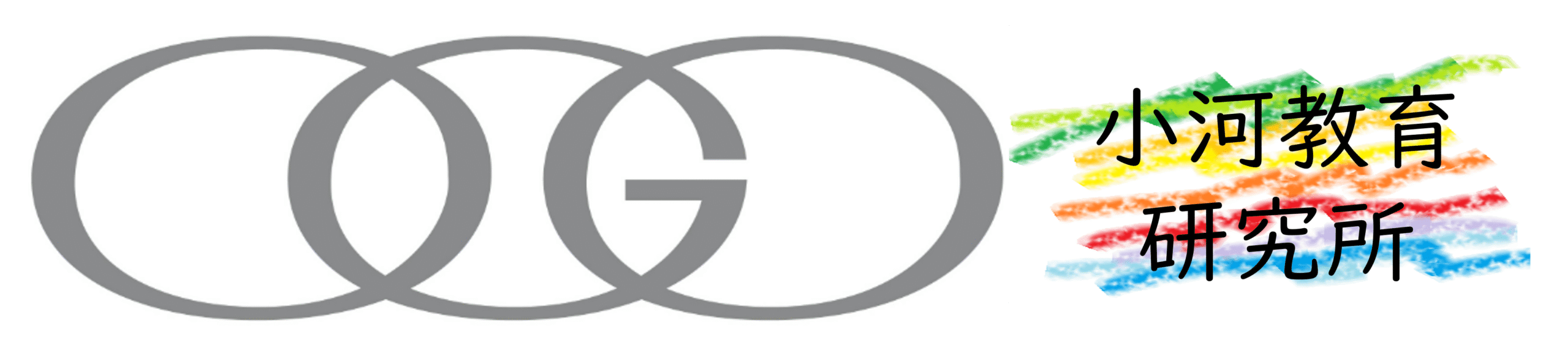記事をお読みいただきありがとうございます。
突然ですが、学校で3・3モジュールを実施してみたいと思ってくださっている先生方に是非やってみていただきたいことがあります。
それは、「変化のデータを取る」です。
「取り組みを始める前(Base Line)」と「取り組みをした1年後(End Line)」で同じレベルのチェック問題を行い、点数を比較します。チェック問題は無料でダウンロードできるようにしますので、是非、使ってください。
なぜ、これが大事か?
「データ」があると人を説得できるからです。
当然ですが基礎学力向上の取り組みは続ける必要があります。続けるためには「効果があるぞ」ということを出来るだけ早く示す必要があります。しかし、学校現場で新しい取り組みを導入することは簡単なことではありません。大人数の組織というものは従来の安全な方法に固執しやすいからです。教師同士の考え方の違いから協力を得られないことも多々あるでしょう。
孤立無援の状態から出来るだけ早く脱出する必要があります。
取り組みが進めば生徒たちの様子が変わってきます。加えて「データ」の数字で結果を見せれば非常に説得力が増すのです。これは多くの反対意見を浴びながらも「データ」の力に幾度となく後押しされてここまで来れた私の実体験からの話です。
中学校教師時代の私も最初は一人で取り組みを続けていました。そして少しづつ少しづつ、取り組みの効果を目にした他の先生方が加わって、徐々に学年全体での取り組みになっていきました。そして最終的には文科省や大阪府を動かす大きな社会的動きに発展したのです。(詳しくはBlogに書いていますのでそちらで)
海外の学校で指導を行う場合も同じです。データの取り方が要になります。もっとも致命的なことは「取り組み前のデータ(Base Line)を取れない事」です。過去にさかのぼって0の状態を測定することが出来ないからです。
私は学生一人一人に対して自分の記録をつけ、その変化を分析するように伝えています。一方、先生方が行う記録とデータ分析はもっと大きな規模であり、保護者の方々や学校組織に対して取り組みの有効性を証明できる重要な資料になるのです。データはそれ自体が即効性のある大きな力になる可能性を持っています。
そこで、ここではクラスや学年単位で行える効果的なデータの取り方、多人数を相手に3・3モジュールを実施するコツとメリットについてお話していきます。
- 取り組みの前後で行う調査(Base Line と End Line)
- 取り組みの中で行うデータ収集 (Time、誤答数、自己管理)
- グループダイナミクスの効果を利用する