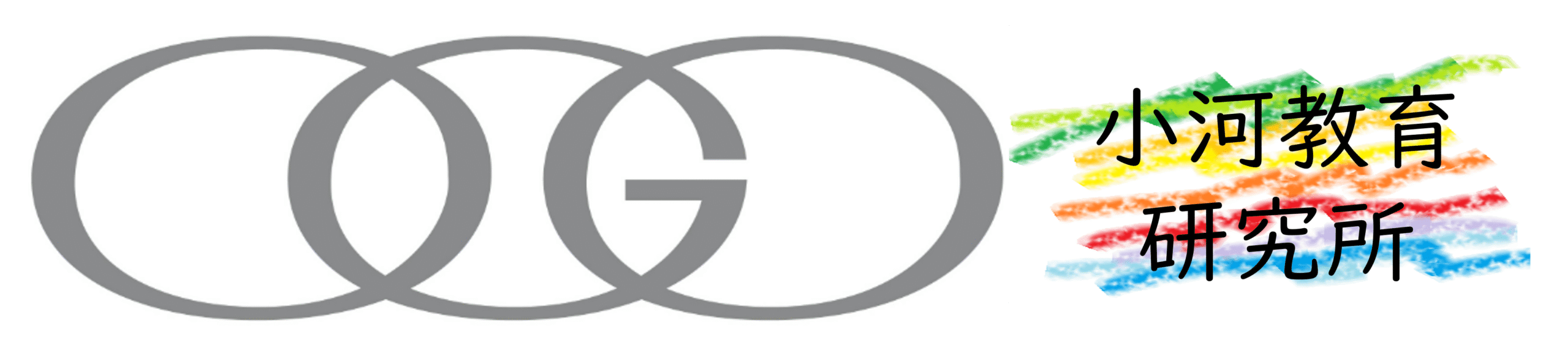大学生が四則計算できない本当の理由 ― 教育改革が招いた半世紀の影響
今年7月15日の朝日新聞に「大学で四則計算!」という記事が掲載され、同じ内容が8月19日に毎日新聞にも取り上げられました。
「大学生が+、-、✕、÷ができない」という衝撃的な内容です。
大学生が四則計算できないという現実
実はこの問題は、ずっと前から全国の大学で深刻な課題となっていました。
7年前、私は大学協会に講師として招かれ、このテーマについて講演しました。会場は広島の修道大学。全国から約200名の大学関係者が集まり、決して数校に限った特殊な問題ではないことを痛感しました。
つまずきは小学校から始まっている
中学校の現場で私は日々、膨大な「つまずき」に直面してきました。
そして気づいたのです。つまずきは自然には解消されず、大学生、さらには社会人になっても続くのだと。
実際、四則計算でつまずいた学生は、分数・小数・%・比例・グラフ・図形など、小学校算数の基礎が身についていません。
その結果、中学校の一次方程式や高校数学も理解できず、大学の学習にも深刻な支障をきたすのです。
1971年の学習指導要領改訂が転機
では、なぜ日本でこのようなことが起きたのでしょうか。
原因のひとつは、1971年度の学習指導要領の大改訂にあります。
この改訂で、低学年の算数学習が「3年かけて行っていた内容を1年で終える」形に変更されました。
繰り上がり・繰り下がり・九九が定着しないまま次へ進むことになり、子どもたちは「分かったつもり」でも本当に使える力にはならなかったのです。
教育界からは大きな反対運動も起きましたが、国会で強行採決され、多くの子どもたちが基礎を身につけられないまま進級することになりました。
「荒れる中学生」の登場
その結果、6年後の1977年、中学校には基礎学力を欠いた世代が入学してきます。
立正大学・鬼頭教授の研究でも、ちょうどこの年から非行少年数が急増していることが示されています。
私自身も中学校教師として、その変化を肌で感じました。
それまで牧歌的だった学校生活が、1977年から急に一変。整列しない、指示を聞かない、生徒による暴力や授業妨害…。
中学校全体が一気に荒れ始めたのです。
今に続く教育の空洞化
それから半世紀が経ち、何度か指導要領の改訂や「ゆとり教育」の試みもありました。
しかし根本的な問題――基礎学習を空洞化させた「教育の現代化」の影響は解消されないままです。
塾や家庭教師で救われる子は一部にすぎず、多くの子どもが切り捨てられています。
私は自らの経験から、子どもの99%は正しい方法で育てれば必ず「できる」ようになると確信しています。
にもかかわらず、現状では1~2割が生き残るだけで、残りは見捨てられてしまっているのです。
教育を立て直すために
国家の基礎教育は「すべての子どもに基礎を身につけさせる」ことが本来の使命です。
しかし、今の教育制度はそれを果たせていません。
基礎を身につけられなかった子どもたちは、その後の学習や人生に大きなハンディを背負います。
そして社会全体も、若者の無気力・理由不明の犯罪・不登校・いじめなどの形でその影響を受けています。
私は、これらの制度的な問題に対して今後も声を上げ続けなければならないと考えています。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 お勧め記事2025年12月31日「これで大丈夫?」に答えます。親子で取り組む「3日間繰り返し学習・超基礎編」 Q&A
お勧め記事2025年12月31日「これで大丈夫?」に答えます。親子で取り組む「3日間繰り返し学習・超基礎編」 Q&A お勧め勉強方法2025年12月31日「100マスまで」の本:親子で毎日少しづつ、低学年から育てる基礎計算力
お勧め勉強方法2025年12月31日「100マスまで」の本:親子で毎日少しづつ、低学年から育てる基礎計算力 お知らせ2025年10月26日ブログ◆4:アフリカでの「指計算」の話
お知らせ2025年10月26日ブログ◆4:アフリカでの「指計算」の話 お知らせ2025年10月26日ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い
お知らせ2025年10月26日ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い