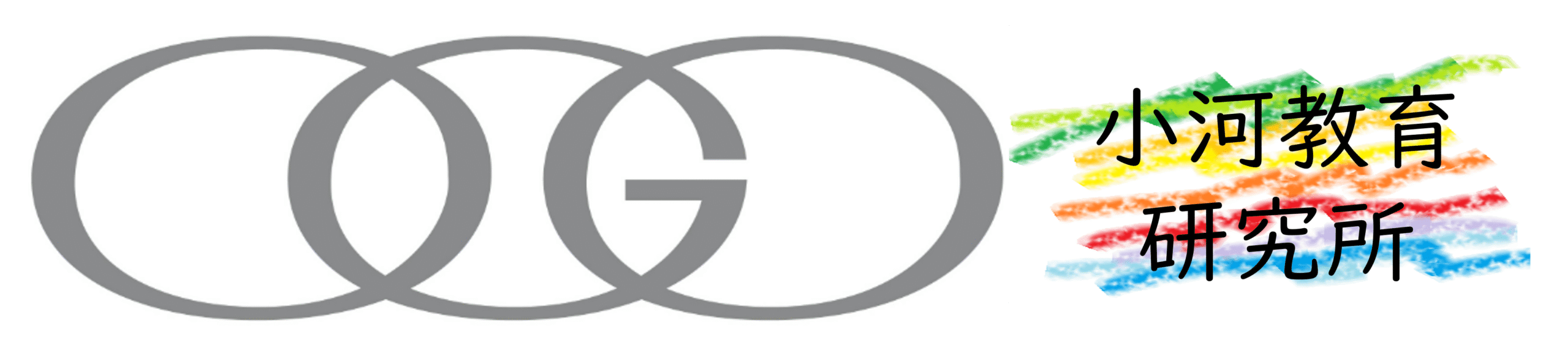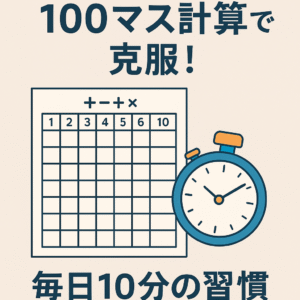「小1のつまずき」が学力差を広げる──算数・国語で見落とされがちな基礎定着の重要性"
"小学校1年生からの学習のつまずきが、後の学力差につながります。特に算数や国語の基礎定着の不足が、子どもの学習意欲や理解力に影響。保護者ができるサポートの工夫について解説します。"
「小1のつまずき」が学力差を広げる──算数・国語で見落とされがちな基礎定着の重要性
はじめに
「うちの子、勉強が苦手かも…」そう感じるのは、中学や高学年になってからではありませんか?
実は、学力差の始まりは小学校1年生のころに生まれることが多いのです。
小学校低学年で身につけるはずの基礎がしっかり定着していないと、後の学習に大きな影響が出ます。これは特に算数や国語で顕著に表れます。
なぜ「小1のつまずき」が大きな差になるのか?
1. 学習は積み重ねだから
算数では「数の合成・分解」を理解できないまま進むと、繰り上がりや掛け算・割り算にスムーズに入れません。
国語では「音読のつまずき」があると、漢字や文章理解に影響します。
2. カリキュラムの進度が早い
学校では毎年新しい内容を学び続けます。復習の時間が十分に確保されないため、一度つまずくと次の単元についていけなくなることが多いのです。
3. 家庭環境の差が広がる
「復習は家庭で」というスタンスのため、保護者のサポート有無がそのまま学力差につながるケースもあります。
算数で見落とされがちな基礎
算数の基礎は「+」「-」の計算だけではありません。
- 「8+7」を「8+2+5 → 10+5 → 15」と工夫できるか
- 指を使わずに数を頭の中で処理できるか
こうした数のイメージ力が育っていないと、計算が遅くなり、文章題や応用問題で苦戦するようになります。
国語で見落とされがちな基礎
国語では、ただ文字が読めるだけでなく、意味を理解しながら読む力が大切です。
- 音読を「ただ声に出す」だけで終わらせない
- 読んだ文章を自分の言葉で説明できるか確認する
この積み重ねが「読解力」の土台となり、中学以降の学習に直結します。
保護者ができるサポート
1. 毎日の小さな習慣を大切に
- 10分でもいいので「計算練習」や「音読」を続ける
- 「できた!」を一緒に喜ぶ
2. 苦手を早めにキャッチ
「計算に時間がかかる」「音読がぎこちない」と感じたら、その時点で補強してあげましょう。
3. 学校任せにしない
学校の授業だけでは基礎定着が保証されません。
親が「今どこでつまずいているのか」を見守ることが大切です。
まとめ
小学校1年生の基礎がしっかり定着しているかどうかが、後々の学力差を大きく左右します。
算数では「数の感覚」、国語では「意味を理解する読解力」がポイントです。
保護者ができるのは、毎日の小さな習慣を支え、子どもの「できた!」を一緒に積み重ねていくこと。
中学で大きな差にならないよう、今の小さなつまずきを見逃さないことが何より大切です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 お勧め記事2025年12月31日「これで大丈夫?」に答えます。親子で取り組む「3日間繰り返し学習・超基礎編」 Q&A
お勧め記事2025年12月31日「これで大丈夫?」に答えます。親子で取り組む「3日間繰り返し学習・超基礎編」 Q&A お勧め勉強方法2025年12月31日「100マスまで」の本:親子で毎日少しづつ、低学年から育てる基礎計算力
お勧め勉強方法2025年12月31日「100マスまで」の本:親子で毎日少しづつ、低学年から育てる基礎計算力 お知らせ2025年10月26日ブログ◆4:アフリカでの「指計算」の話
お知らせ2025年10月26日ブログ◆4:アフリカでの「指計算」の話 お知らせ2025年10月26日ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い
お知らせ2025年10月26日ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い