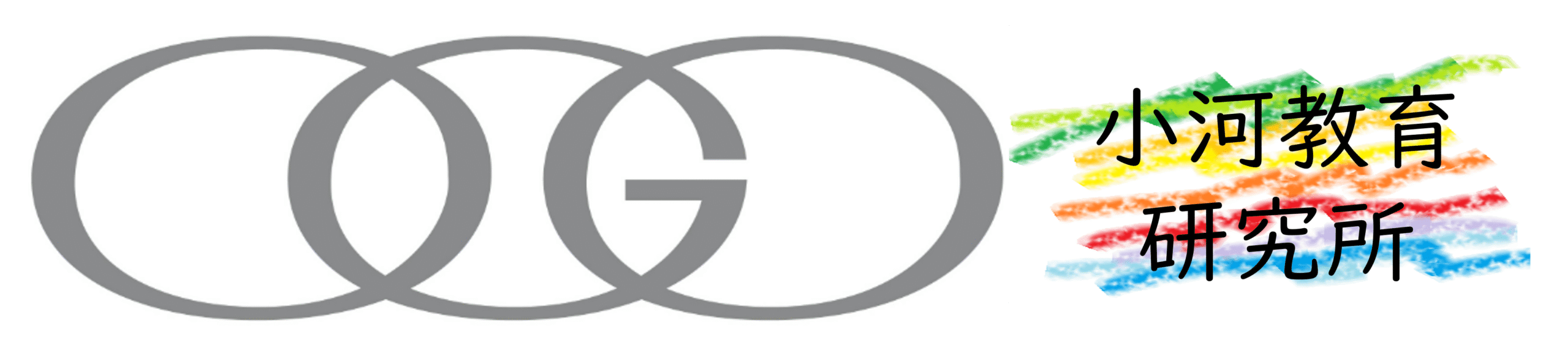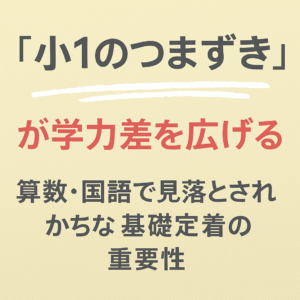子どもが算数につまずいたときに保護者・教師ができること
「大学生なのに四則計算ができない」という話題を耳にしたことはありませんか。実はこれは珍しいことではなく、教育現場では深刻な課題になっています。子どものころに算数の基礎でつまずいた経験が、そのまま大人になっても尾を引いてしまうのです。
なぜ子どもは算数でつまずくのか
多くの子どもがつまずくポイントは決まっています。代表的なのは次のような場面です。
- 繰り上がり・繰り下がりのある計算
- 分数と小数の計算
- 割合や比例
- 文章題やグラフの読み取り
これらは小学校算数の基礎ですが、ここで理解が不十分なまま進むと、中学・高校、さらに大学に入っても「四則計算ができない」状態につながってしまいます。
つまずきの背景 ― 制度の問題もある
1971年の学習指導要領改訂以降、「ゆとり」の流れが強まり、基礎学力の定着がおろそかになりました。教育の問題は、決して子どもの性格や努力不足だけではありません。制度的な背景も理解することで、保護者や教師は「できないのは本人のせいではない」と捉えやすくなります。
保護者にできること
子どもが算数につまずいたとき、家庭でできるサポートのポイントは以下の通りです。
- わからないところまで戻る勇気を持つ └ 割合でつまずいていたら、分数やかけ算九九に戻ってOK。
- 指や具体物を使った計算を恥ずかしがらせない └ 頭の中だけで処理できなくても大丈夫。「できた!」の積み重ねが大切です。
- 短時間で区切って練習する └ 毎日5分でも継続すれば大きな力になります。
教師にできること
現場の教師が子どもを支援する際は、次の工夫が有効です。
- つまずきの根っこを探る └ 割合ができない子は、実は「繰り下がり」でつまずいていることも多いです。
- 小さな成功体験を積ませる └ 簡単な問題から取り組ませ、「わかる!」「できた!」を実感させましょう。
- 諦めムードを防ぐ └ 「算数が苦手な子どもは一生苦手」という誤解を、教師自身が持たないことが大切です。
まとめ ― 誰でもやり直せる
大学生でも四則計算ができない時代ですが、それは子どものころの「算数のつまずき」を放置した結果です。逆に言えば、保護者と教師が手を取り合って基礎に立ち返れば、どの子も計算力を取り戻せます。大切なのは「本人のせいにしない」ことと、「小さな成功を一緒に喜ぶ」ことです。今日からできる小さな支援が、子どもの未来を大きく変えていきます。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 お勧め記事2025年12月31日「これで大丈夫?」に答えます。親子で取り組む「3日間繰り返し学習・超基礎編」 Q&A
お勧め記事2025年12月31日「これで大丈夫?」に答えます。親子で取り組む「3日間繰り返し学習・超基礎編」 Q&A お勧め勉強方法2025年12月31日「100マスまで」の本:親子で毎日少しづつ、低学年から育てる基礎計算力
お勧め勉強方法2025年12月31日「100マスまで」の本:親子で毎日少しづつ、低学年から育てる基礎計算力 お知らせ2025年10月26日ブログ◆4:アフリカでの「指計算」の話
お知らせ2025年10月26日ブログ◆4:アフリカでの「指計算」の話 お知らせ2025年10月26日ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い
お知らせ2025年10月26日ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い