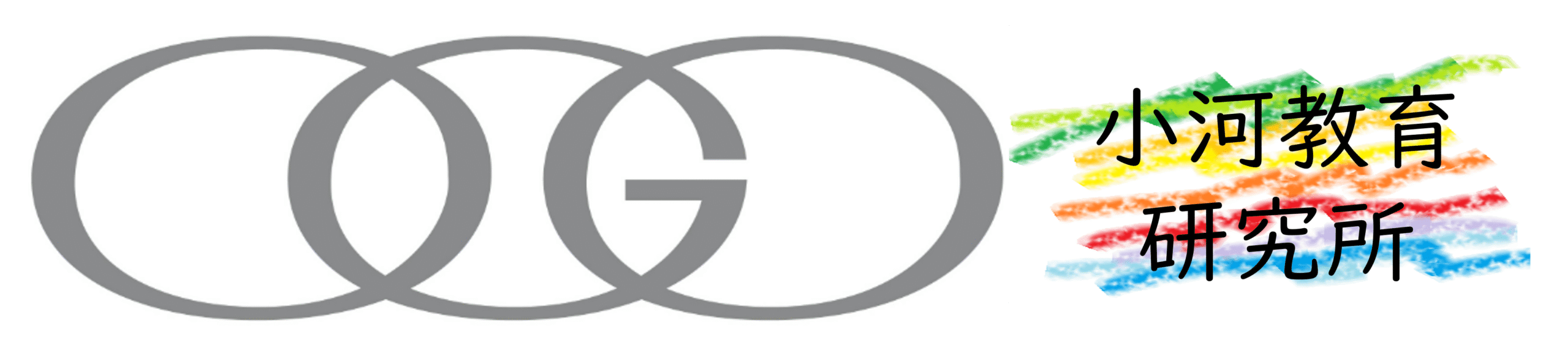指計算(指でカウンティング)の子が7割も!
小学校1年生11月の段階で、指計算(指で数えながら計算する)をしている子が7割もいるという事実をご存じでしょうか。
これは私が視察したある学校でのことです。経験豊かな先生に尋ねると「7割ですね」と即答されました。実際に子どもたちにドリルをさせてみると、本当にほとんどの子が指でカウンティングをしていました。
別の学校でも2年生の春の段階で6割が指計算をしていました。つまり、大部分の子どもが指計算で学んでいるのが現実なのです。
指計算は自然になくなる?それとも危険?
「指計算は続けていれば自然にやめる」と思われがちですが、私はそうは考えていません。
- 指計算は確実な方法なので、特に慎重な性格の子ほど抜け出しにくい
- 学年が進むと算数の進度は加速度的に速くなる
- 指計算のままでは計算速度が追いつかず、授業が理解できなくなる
つまり、指計算は放置すると自然に消えるどころか、算数のつまずきの原因になるのです。
「大学で四則計算!」新聞記事が示す現実
2025年7月、朝日新聞・毎日新聞に「大学で四則計算を指導する必要がある」という記事が掲載されました。
大学教授は「詰め込み教育のせい」と解説していましたが、私は違うと考えています。
問題は小学校での計算練習時間の不足です。
実際に30年以上前から、大学では「四則計算ができない学生」が深刻な問題として協議されています。
つまり、小学校で克服できなかった指計算の問題は大学まで続くということです。
指計算をしていないように見えても要注意

「うちの子は指を使っていない。でも計算が遅い…」というケースもあります。
実は、子どもは恥ずかしさから指を使わず、頭の中でカウンティングしている場合があるのです。
これが一番危険です。なぜなら、頭の中で数えるとスピードも精度も落ちやすいからです。
一般的な計算方法(合成分解)とは根本的に異なるため、早期に修正する必要があります。
家庭でできる確かめ方のポイント
お子さんが指計算をしているかどうかを調べるには、**「何も言わず、そっと観察する」**ことが大切です。
※このチェックをするためのドリルを添付しますので、ぜひ試してみて下さい。次回のブログで、具体的なドリルの使い方や見方を紹介いたします。
チェック方法
- 簡単な「+」「―」の計算プリントを渡す
- 特に「繰り上がり・繰り下がり」の問題に注目する
- グレー部分(課題箇所)で手が止まったり遅くなる → 指計算の可能性大
保護者が注意すべき点
- 子どもに「見られている」と悟られないこと
- 声かけやアドバイスは一切しないこと
- ただ黙って観察すること
これだけで指計算かどうかのヒントが得られます。
子どもを責めずに、温かく見守ることが大切
指計算をしているのは「頭が悪い」からではありません。
単に「繰り上がり・繰り下がり」でつまずいているだけです。
ドリルで段階を踏んで練習すれば、必ず克服できます。
保護者の方にお願いしたいのは、**「優しく・ゆっくり」**サポートすること。
子どもは必死に崖から這い上がろうとしています。
どうかその気持ちに寄り添い、温かく見守ってあげてください。
まとめ
- 小1の7割が指計算をしている
- 放置すれば自然に直らず、大学まで続くこともある
- 指を使っていなくても頭の中でカウンティングしている場合がある
- 家庭でのチェックは「何も言わず、そっと観察」が鉄則
- 攻めずに支えれば、必ず改善できる
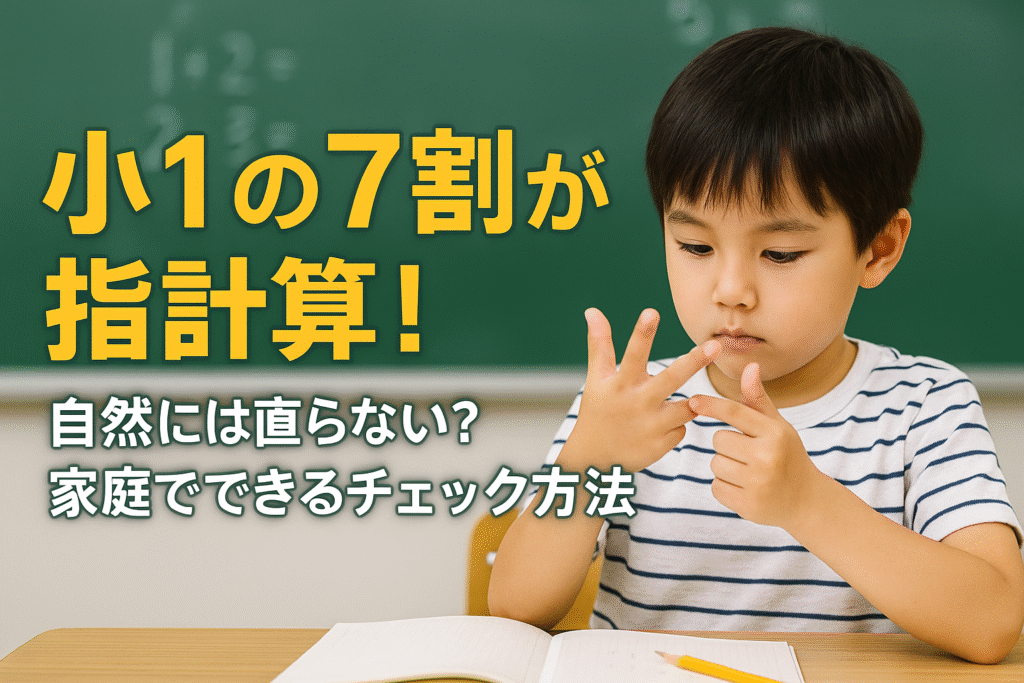
投稿者プロフィール
最新の投稿
 お勧め記事2025年12月31日「これで大丈夫?」に答えます。親子で取り組む「3日間繰り返し学習・超基礎編」 Q&A
お勧め記事2025年12月31日「これで大丈夫?」に答えます。親子で取り組む「3日間繰り返し学習・超基礎編」 Q&A お勧め勉強方法2025年12月31日「100マスまで」の本:親子で毎日少しづつ、低学年から育てる基礎計算力
お勧め勉強方法2025年12月31日「100マスまで」の本:親子で毎日少しづつ、低学年から育てる基礎計算力 お知らせ2025年10月26日ブログ◆4:アフリカでの「指計算」の話
お知らせ2025年10月26日ブログ◆4:アフリカでの「指計算」の話 お知らせ2025年10月26日ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い
お知らせ2025年10月26日ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い