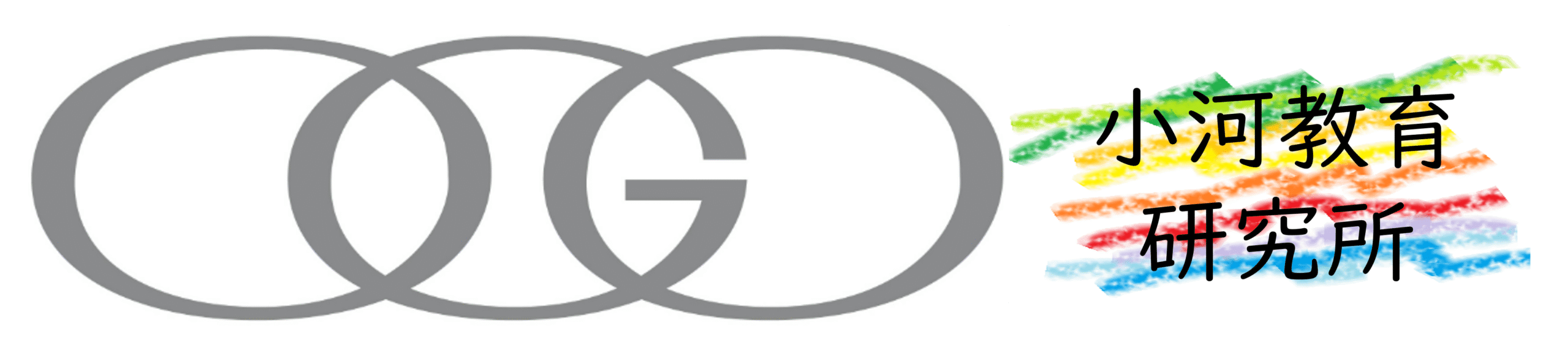国内での活動
・大阪府:2014年秋、大阪府の学力が全国学力テストで全国の最下位から3番目の低さとして発表される。当時大阪府の教育委員であった私はその改善を求められ、府下の300校の中学校の校長を集めて学力向上の方策として各校でのモジュールの実施を呼びかける。秋から翌年春にかけ、半年間の取り組みが行われ、翌年秋、大阪府は全国平均近くまで成績は上昇したことが報じられた。
・樟蔭学園中等部:大阪の私立校である同校で2008年、中学1年生に対しモジュールの授業を取り組む。朝の数学、帰りの国語と一日2回の取り組みで実践。その成果は明確に表れる。この成果は大学への受験と合格率の劇的な変化となるだけでなく、学生たちの心理的健全化(心理的不安で通う生徒が4分の1以下になるなど保健室の利用度が大幅に変わる)や、部活での変化(全国優勝が3クラブ、それも毎年)として現れる。これは2023年1月NHKテレビで報道された。
・福岡県:2012年より二つの市で全中学校の学力向上に対し取り組んでいる。
・山口県山陽小野田市:2006年、文科省の研究指定として山口県山陽小野田市教育委員会では市内の全小学校でModuleを実施。小河はその監督にあたる。同市の3700人の全児童(1年生から6年生まで)に対して、100マス計算15分。音読15分、計30分間の授業を1単位とし、これを週3回、1年間、8カ月間行い、知能指数(IQ)の変化を測定。その結果、平均で9ポイントのIQ上昇という結果を得た。開始時点で成績が良かった生徒だけでなく、成績が低かった生徒も等しく変化するという驚くべき結果となった。
海外での活動
・マラウィ(JICA):JICAプロジェクトで東アフリカのマラウィで取り組み、大きな成果を得る。
・インドネシア(JICA):2012年~2013年JICAのBOPプロジェクトでインドネシアで挑戦する。1年間の取り組みで劇的な成果を収める。
➡ 詳しくはこちら
・南アフリカ:JICAプロジェクトで南アフリカのハウテン州にて1年間取り組みを行う。
・スリランカ(JICA):2005年、スリランカにてJICAプロジェクトに要請を受け参加
・課題別研修(JICA):2022年、エジプト、ザンビア、シェラレオネ、ミクロネシア、ラオス、バングラディッシュ、ネパールパキスタンの教員16名に対して基礎学力向上に向けた1カ月間のWeb研修を実施。
小河勝の経歴
信州大学文理学部自然科学科(理学部)卒業。
1,972年より大阪市内で32年間中学校教員を務める。主に生活指導で生徒会指導の担当。
1977年から「中学の荒れの到来」という暴力的事態に翻弄される。結局管理だけで抑えようとしても生徒たちの怒り、もがきの原因は勉強が分からないという子どもたちの「絶望感」に根差すこと、即ち「学力づくりが解決策である」と分かる。
1978年教師で作る「落ちこぼれ研究会(落ち研)」の100マス計算を知り、それを組み込んだ繰り返し学習法を開発。
1990年読売新聞に短時間繰り返し学習法(モジュール)の実践が紹介される。
1990年「わが子は中学生」に「学力づくりと家庭づくり」を2年間連載。月一回。全国で3万冊。
1991年同記事内で紹介した学習効果を示したグラフについて説明して欲しいと100マス計算の開発者である岸本先生に「落ち研」の合宿に招かれ、そこで陰山君と知り合い、彼が勤務する丹波篠山市の小学校に招かれ教師たちへの研修を指導する。その後、陰山君の実践を指導する状態が10年間ほど続く。
2003年「学力低下を克服する本」(文藝春秋社刊)を出版。ありがたいことに20万部のベストセラーとなった。
同年7月「中学数学基礎篇」。12月「中学国語基礎篇」を文藝春秋社から出版。
2005年教員退職。和歌山大学教育学部非常勤講師、樟蔭女子大学非常勤講師。
同年10月よりSri LankaでのJICAprojectに専門家として参加。(2008年まで)
同年10月、大阪ナンバにて「小河学習館」を設立。特に「親子で取り組む家庭学習」をテーマに希望者のニーズに合わせて個別対応を展開。
2008年、大阪府教育委員就任。2016年10月まで2期8年間委員長職務代理。
2009年、1月11日。指導要領改訂の時期にあたり、文科省に対し授業時間の分割実施合法化の交渉を直接行う。その結果、「短時間、繰り返しの帯学習」の実施が可能になったことが指導要領に明記される。この「短時間連続繰り返しの帯学習の形式」は後に文科省が「モジュール」と命名する。
2010年 「学力低下を克服する本」の出版を契機に「3・3モジュール」を出版する。
2010年 学習塾「奈良ゼミナール」を奈良市富尾駅前に開く。
2013年 Indonesiaにて劇的な学力アップを達成、JICAで報告。
2014年 JICA「基礎教育事業支援委員会委員(全国で8名)」発足、委員となる。
2015年 JICA「課題別研修 基礎計算力向上コースリーダー」就任。同研修開始。
2016年 マラウィでJICAの仕事で基礎計算力向上の活動に取り組む。
2023年 JICA啓林館プロジェクトで南アに専門家で参加。