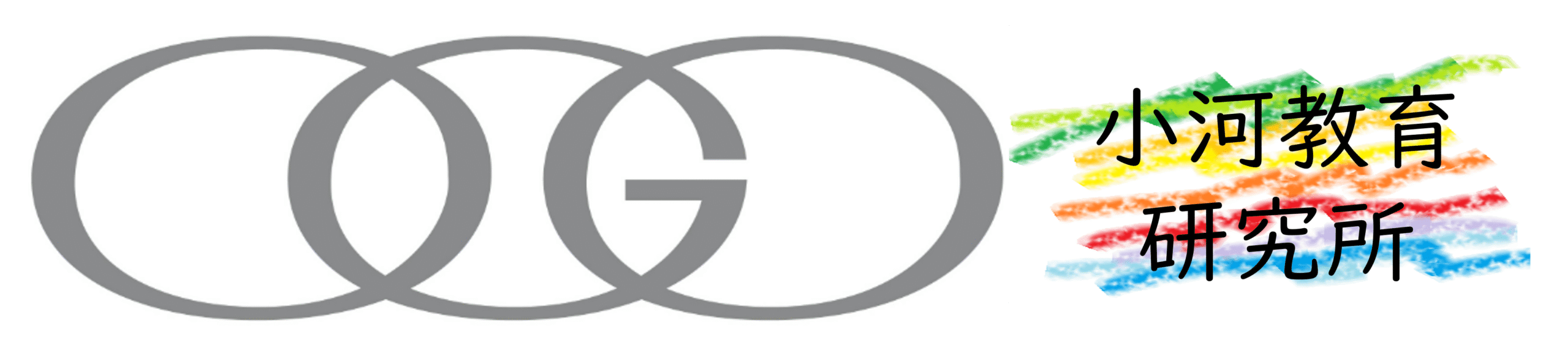ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い
◆3「指計算」と「合成分解」の違い
私たち日本人の大人が普通やっている計算方法は「合成分解」といいます。「指計算」と「合成分解」とどのように違うか、ここで先ず確認しておきましょう。これが明らかになれば「なんだ」と言われそうです。
「合成と分解」の考え方・・実例
例えば実際にそのままの数の鉛筆を見せて
「8本の鉛筆と7本の鉛筆があります。足すと何本ですか?」を考えてみましょう。
★指計算の場合
★「指計算」では8本のグループを一本ずつ指で数えていき、最後は8。続いて7本のグループを数えます。この時、7本のグループの最初は「9番目」になります。次は「10、11,・・15」で終わり。答え「15本」という訳です。
この数え方は物と数とを、いちいち対応させるため確実です。ですから、どの子も数えるということができるようになると、4~5歳の子でもできるのです。数える計算方法は、必ずどの子もが通る過程なのです。
★「合成分解」の場合
★「合成分解」で計算する場合は、何よりもまず目で数を瞬時に捉えます。
8本のグループは5本と3本に分け、8本だと目で視覚で瞬時に認識します。7本は5本と2本に分け7本だと一瞬でキャッチします。
「8本にはあと2本で10本」(10の補数を考えつくのです)だから「7本のグループは2本と5本に分け」「8本と2本を合体させて10本を作る」。「残りの5本と合わせて15本」と言う訳です。
二つのやり方の違い、わかりますね。次の段階(合成と分解)に進むと瞬時にひらめく計算方法です。
数の概念が(10の補数な数の面白さが分かってくると)「指計算」から「合成分解」に子どもたちが次第に切り替わっていくことも納得がいきます。
「指計算」と「合成分解」のもうひとつの違い
ここで、この二つのやり方の違いをよく見ておきましょう。
「指計算」は遅いということが難点です。でも一本ずつ数と対応させてかぞえるから絶対に確実です。
「合成分解」は一見ややこしいように見えて、目で見て数を判断し、計算処理するからとても速いのです。しかもこの計算処理の方法は繰り返し練習すればするほど速くなります。
やればやるほど速くなる 論理的思考
「8+2⇒10」「7⇒2+5」「10+5⇒15」という数の操作は極めて論理的です。
100マス計算で色々な数同士の組み合わせでこの合成、分解を練習し、どんどん早くなっていくことは、脳のニューロンという神経組織を鍛えます。神経網の広がりを拡大し、神経自体を太くします。このことは実験で証明されていますのでいつかお見せしましょう。
「指計算」(カウンティング)は「量」ではなく「順番」を数えている
もう一点重要なことがあります。
「指計算」のカウンティングは順番を数えているということです。先ほどの問題で最後に「15」という数字を得ることができました。しかしこの数字は15番目という意味なのです。「50」であっても「100」であっても数字はすべて順番を意味するのです。15本という「量」ではないのです。このことは実は重大な問題を意味することになります。この点についての説明も後程詳しく行いましょう。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 お勧め記事2025年12月31日「これで大丈夫?」に答えます。親子で取り組む「3日間繰り返し学習・超基礎編」 Q&A
お勧め記事2025年12月31日「これで大丈夫?」に答えます。親子で取り組む「3日間繰り返し学習・超基礎編」 Q&A お勧め勉強方法2025年12月31日「100マスまで」の本:親子で毎日少しづつ、低学年から育てる基礎計算力
お勧め勉強方法2025年12月31日「100マスまで」の本:親子で毎日少しづつ、低学年から育てる基礎計算力 お知らせ2025年10月26日ブログ◆4:アフリカでの「指計算」の話
お知らせ2025年10月26日ブログ◆4:アフリカでの「指計算」の話 お知らせ2025年10月26日ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い
お知らせ2025年10月26日ブログ◆3「指計算」と「合成分解」の違い